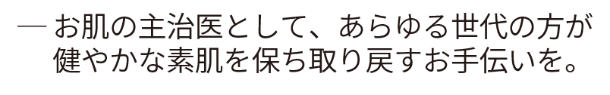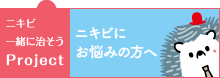稗粒腫について
稗粒腫について
本日は稗粒腫(ひりゅうしゅ・はいりゅうしゅ)についてご説明いたします。
稗粒腫とは
稗粒腫は目の周りや、顔にできる白い粒のようなものです。
直径1~2㎜程度の大きさで、袋の中には角質が入っています。

原因
・毛穴の奥にある毛包(もうほう)という袋や、皮脂をつくる腺の未発達なものに角質がたまって生じます。
・汗を出す管の再生過程で管の先端がふさがって生じます。
治療方法
注射針の先で皮膚の表面に小さく傷をつけ、白色の球状物を押し出します。
痛みなどはないため放っておいても問題はありません。
気になる症状がございましたらご相談ください。
2022/03/23
粉瘤について
粉瘤について
こんにちは
暖かく過ごしやすい季節になってきましたね
本日は「粉瘤(ふんりゅう)」についてご説明致します。
粉瘤とは?
本来皮膚から剥がれ落ちるはずの垢や皮脂などの老廃物が皮膚の内部にたまることによってできる、良性の腫瘍のことです。
粉瘤はアテロームとも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造物ができます。
初めは非常に小さいため、自覚される方はほとんどいません。
しかし溜まった垢や皮脂は自然に袋の外には出られず、どんどん溜まっていきます。
その為、時間と共に少しずつ大きくなっていきます。
できやすい部位
身体のどこにでもできます。
耳の後ろや脇の下、鼠径部(足の付け根)や背中などにできやすい傾向があります。
症状
普段は痛みなどの症状はありません。
しかし、細菌が侵入して化膿する場合があります。
これを「炎症性粉瘤」と呼び、患部は赤く腫れ、痛みを伴います。

治療
軽い炎症の場合は抗生物質や痛み止めの内服を処方します。
強い炎症を伴う場合は局所麻酔を使用し、皮膚を小さく切開し膿を外へ出す処置をします。
根治的な治療をするためには、外科的に袋ごと取る手術をします。
炎症が起きているときには、外部の組織と癒着を引き起こしているため切除ができません。
内服や外用薬で炎症が落ち着かせてから手術を行います。
そのため、腫れと痛みで「今すぐ取りたい!」というときに根治的治療ができません
粉瘤はほとんどが良性腫瘍のため、必ず手術をしなければいけないということではありません。
しかしどんどん大きくなったり、再発を繰り返すため、切除をお勧めする場合がございます。
小さいうちに摘除をすると傷跡が小さく済むため、早めの手術を検討しましょう
当院では、月に1回程度外来手術を行っております。
詳しい内容についてはスタッフへご相談ください
気になる症状がございましたら、お早めにご相談ください
2022/03/16にきびについて②
◎ニキビの治療
赤いニキビには炎症を抑えるお薬が処方されます。
しかし赤いニキビを治しても、ニキビはコメドがあると再発します。
コメドの状態から正しくケアしていくことが重要となります。
ニキビは短期的だけではなく、長期的な治療が必要です。
当院では、医師がひとりひとりの肌の状態を診察し治療を行います。
ニキビでお悩みの方はお気軽にご相談ください♪
◎ニキビを悪化させないために
ニキビを触ったり、つぶしたりすると、化膿してニキビ跡を残す原因となることがあります。
洗顔や保湿などのスキンケアやお薬を塗るとき以外は触らないように気をつけましょう。
甘いものや脂っこいものの食べ過ぎニキビが悪化すると言われていますが、はっきりとしたデータがあるわけではありましせんが、健康な肌を保つためには、ビタミン豊富な緑黄色野菜や、食物線維を含んだ食物など、バランスのとれた食事の重要です。さらに睡眠をしっかりとって、規則正しい生活を心がけましょう!
ニキビくらいで皮膚科を受診してもいいのか?など、悩まれる方もいらっしゃると思いますが、ニキビは悪化する前に治療を行うことが大切です。
ぜひ一度ご相談ください(^^)☆


ニキビについて①
◎にきびとは?
にきびとは毛穴にできる病気です。
皮膚を保護するあぶら分(皮脂)がでる毛穴は、思春期になると大きく発達して皮脂をたくさん作れるようになります。
ニキビが出来やすい顔・胸・背中にはこの毛穴がたくさん集まっているため、ニキビができやすくなっています。
◎ニキビの原因
ニキビには「皮脂分泌の増加」「毛穴のつまり」「アクネ菌の増殖」が関係しています。
ニキビは皮脂により毛穴がつまってしまい、皮脂がでられずに溜まってしまうことから始まります。
この状態を「コメド(面ぽう)」と呼びます。コメドの中はアクネ菌の発育にてきした環境のため、どんどんアクネ菌が増えていき、悪化してしまうこともあります。
◎ニキビの状態
ニキビは炎症の程度などによって状態が異なります。
*炎症のないニキビ
①白ニキビ
→毛穴に皮脂がたまり、アクネ菌が増え始めます
②黒ニキビ
→白ニキビの毛穴の毛穴が開き黒くみえます。
*炎症を起こしたニキビ
③赤ニキビ
→アクネ菌が炎症を引き起こします。
④黄ニキビ
→赤ニキビが悪化し、化膿した黄色くみえます。
⑤治癒(炎症を起こした後は赤みが残りますが、目立たなくなり治ります)
※適切な治療を行わないとデコボコと「瘢痕」が残ることもあります。
次回はニキビの治療についてご説明します(^0^)!


スキンピールバー石鹸のご紹介♡
当院では、自費でご購入いただけるスキンケア商品を数多く取り揃えております♪
今回は、その中でも人気がありロングセラーのサンソリットスキンピールバー石鹸をご紹介します!
スキンピールバー石鹼は、サンソリットと皮膚科専門医との共同開発によって誕生したピーリング石鹸です。
*ピーリングとは?*
肌表面にたまった古い角質を刺激の少ない酸(AHA=グリコール酸)などで無理なく離し、
しっかりと洗浄することによってくすみや汚れを取り去り、様々なトラブルからお肌を守る美容法です。
スキンピールバー石鹸は、肌質やお悩みによって4種類のタイプがございます。
◆乾燥、敏感肌用には「青」 大:2160円(税込) 小:300円(税込)
グリコール酸0.6%配合のピーリングソープ。
きめ細かな泡で古い角質を洗い流します。ピーリングビギナーにおすすめです。
◆普通肌用には「緑」 大:2160円(税込) 小:250円(税込)
グリコール酸1.0%配合のピーリングソープ。ピーリングに慣れてきた肌におすすめです。
◆脂性・ニキビケア用には「赤」 大:2700円(税込) 小:350円(税込)
グリコール酸1.0%に加え、ティートゥリーオイル配合。
古い角質を洗い流し、肌を清潔に保ちます。強いピーリング作用があり、背中のニキビケア等にもおすすめです。
◆くすみが気になる方には「黒」 大:5400円(税込) 小:650円(税込)
グリコール酸に加え、肌に透明感を与える成分ハイドロキノン配合。
古い角質を洗い流し、肌に透明感をあたえます。毎日のピーリング洗顔で、透明感のあるみずみずしい素肌へと導きます。
※どのタイプがいいのか迷われたりご不明点がありましたら、お気軽にスタッフにお声がけください。
お求めやすいミニサイズの販売もしていますので、是非お試しください(^^)/

2022/02/09
口唇炎・口角炎について②
前回に引き続き、口唇炎・口角炎の予防法・治療方法についてご説明いたします。
≪口唇炎・口角炎の予防と対策≫
○唇をいじらない、舐めない
乾燥した唇を繰り返し舐めてしまうと唾液に含まれる消化酵素が刺激となり、口唇炎や口角炎を引き起こしやすくなります。
唇が乾燥している時は手で触ったり舐めたりせずにリップクリームなどを使用しましょう。
○ビタミンを摂取する
ビタミンが不足すると口角炎を引き起こしやすくなるため、ビタミンB2・B6を積極的に摂ることをおすすめします。
ビタミンB2はヨーグルト・牛乳・卵・ほうれん草、ビタミンB6は魚・牛肉・豚肉・レバーなどに含まれています。
○十分な睡眠をとり、ストレスや疲労を溜めない
過度のストレスや疲労、睡眠不足は免疫力の低下を招きます。
リラックスできる時間をとったり、気分転換を行うことで心身のリフレッシュを心がけましょう。
○こまめに保湿を行う
唇の乾燥は口角炎や口唇炎の原因となります。
乾燥を防ぐためにリップクリームやワセリンなどの保湿剤を使用しましょう。
≪口唇炎・口角炎の治療法≫
唇を保護する保湿剤やビタミンB群を補う内服薬、炎症を抑えるステロイドの外用薬を使って治療を行います。
少しでも気になる症状がございましたら、お気軽にご受診ください。
2022/01/28
口唇炎・口角炎について①
口元の炎症や痛みに悩まされてはいませんか?
唇は顔の中でも特に皮膚が薄く、敏感な部位の一つです。
今回は口元の代表的な皮膚トラブルである口角炎や口唇炎についてご説明します。
◎口角炎とは?
口角に炎症が起きることで唇の端が赤く腫れたり、かさぶたになったり、皮が剥けたりする症状です。また唇の乾燥により亀裂がはいることもあり、食事の際など口を大きく開けたときに口角が裂けてしまうため、痛みが生じることもあります。
◎口唇炎とは?
唇全体に炎症が生じてしまったり、亀裂がはいってしまう症状です。唇が全体的に乾燥し、腫れや皮剥けを起こしてしまうため痒みを伴うこともあります。
≪主な原因≫
○唇をなめる
唇が乾燥しているときに舐めると一時的に潤ったように感じられますが、舐めることで唇の油分が減ってしまうため、さらに乾燥が進んでしまいます。
その結果亀裂が入ったり、口唇炎を引き起こすなど症状を悪化させてしまうことがあります。
○乾燥
唇が乾燥すると皮膚のバリア機能が失われ、亀裂や炎症が起こりやすくなります。
○ストレスや過労・栄養不足
過度のストレスは免疫低下を招き、ビタミンB2・B6などの不足でも口角炎を引き起こしやすくなります。
口角・口唇炎の治療と予防方法については次回ご説明させていただきます。
2022/01/21
花粉症治療について
こんにちは(^ー^/
前回に引き続き、今回は花粉症治療についてご説明いたします
✿治療
初期療法
花粉が飛び始める前、または症状が軽いうちに治療を始めることを初期療法といいます。花粉が飛散してから治療を始めるよりも、症状が軽くなったり発症を遅らせることができます。
当院では保険内で受けられるアレルギー検査を実施しています。
来院当日採血し、1週間程で結果が出ますので、結果を聞きにいらしていただく流れとなっています。
・毎年決まった時期に鼻のムズムズやくしゃみなど、先に記載した症状が少しでもでる
・昨シーズン、アレルギー症状に悩まされた
・最後のアレルギー検査から数年経っている
・「花粉症かもしれない」と感じることがある
…などの方は一度受診し、症状に適したアレルギー検査をしてみると原因を絞れる可能性があります。
花粉にも様々な種類があり、季節によっても花粉量は変化します。どのシーズンに症状が現れるかは個人差があるため気になる方はアレルギー検査をおすすめします。
✿対症療法
内服薬:抗アレルギー薬を内服し症状を抑えます。副作用で眠気や、他剤と併用可能なのか等生活スタイルに合わせて継続しやすいお薬を医師と選択します。
点鼻薬:鼻スプレーともいい「鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版(改定第8版)」で新たに花粉症の初期療法に用いられる薬のひとつにもなりました。1日1回の噴射で良いものや、小児にも使用可能なお薬があるためご相談ください。
点眼薬:目の痒み、充血、涙がでる方には抗アレルギー点眼薬又はステロイド点眼薬で治療することもあります。
✿花粉症のセルフケア
・外出時にマスク、めがねをして、原因の花粉を少しでも体の中に入れないようにしましょう。
花粉症用のマスクでは花粉が約1/6、花粉症用のめがねでは1/4程度に減少することが分かっています。
・花粉情報に注意し、花粉飛散が多いときには無駄な外出は避けるようにしてください。
・家にいる場合でも、花粉飛散の多いときには窓の開け閉めに注意をしましょう。
・花粉のつきやすいコートを着ることは避けましょう。表面がすべすべした綿かポリエステルなどの化学繊維のものには花粉が付着しにくく、付着した花粉を吸い込む量を減らすことが期待されます。
・外出から帰ってきてもすぐに顔を洗い、うがいをすることをお勧めします。(厚生労働省HPより参照)
全く症状をなくすことは不可能ですが、少しでも症状を軽くすることができると考えます。鼻粘膜の状態を良くするように、悪化の因子であるストレス、睡眠不足、飲みすぎなどを抑えることが必要です。軽い運動などは花粉防御をしたうえでは推奨されると思われます。セルフケアと医師、薬剤師による治療を含め、花粉症の季節を快適に過ごせるようしましょう。

もうすぐ花粉シーズン到来です!
1月も中頃にさしかかり、だんだんと暖かくなってくると花粉の季節がやってきますね。
今年の花粉量などを気にされている方も多いのではないでしょうか。
花粉症のピークは一般的に2~4月といわれていますが、5月も花粉の量や種類が意外と多く、花粉症状が長く続く方もいらっしゃると思います。
花粉症の方は原因となる花粉を見極め、早めに予防や対策を行っていくことが大切です。
<花粉カレンダー>
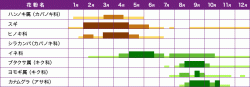
![]()
✿花粉症とは
鼻腔内に入ってきた植物の花粉に対する免疫反応によって鼻水等の症状が引き起こされることをいい、季節性アレルギー性鼻炎とも呼ばれます。
✿症状
1.鼻水
―風邪などによっておこるやや粘性が高く黄・黄緑がかった鼻水とは違い、「水のような」粘り気がなくサラサラした透明のものが止まらずに出てきます。
2.鼻づまり
―鼻粘膜が腫れて鼻からのどへの通り道が狭くなることによって、鼻づまりがおこります。
口で呼吸をしがちになりますので、口の渇き、咳といった症状がでたり、においを感じにくいため食べ物の味が分かりづらくなったりします。
3.くしゃみ
―風邪やインフルエンザの際のくしゃみより回数も多く、ほとんどの花粉症の人が悩まされる症状です。
その他、目の痒み、症状が重くなると、頭痛、だるさ、不眠などを引き起こすこともあります。皮膚の痒みや発疹などの症状が出現している方は花粉皮膚炎の可能性もあります。
✿原因(メカニズム)
空気中に浮遊する花粉が鼻に侵入します
↓
花粉などのアレルゲン(抗原)が鼻腔内の粘膜に付着すると、体内に「抗体」が作られます
↓
抗体がマスト細胞という細胞に結合します
↓
その後再びアレルゲンが侵入すると、マスト細胞からヒスタミン、ロイコトリエンといったアレルギー誘発物質が放出されます
↓
放出されたアレルギー誘発物質が鼻の神経や血管を刺激して,くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー反応が引き起こされます。
次回は花粉症治療についてご説明いたします✿
採血で調べられる花粉症のアレルギー検査も実施しております。皆様のご来店お待ちしております!
2022/01/07低温やけどについて
寒い日が続き、暖房グッズを使うことも多いと思います。今回は寒い時期に増える低温やけどについてお伝えします。
低温やけどとは
低温やけどは、通常ではやけどを起こさないような温度でも長時間触れ続けることによって起こります。カイロや湯たんぽ、電気毛布など体温より少し高めの温度(44-50℃)のものが原因になります。
通常のやけどでは反射的に熱源から離れるため、皮膚が触れている時間は短くなりますが、低温やけどは長時間触れているため、気が付かない間にやけどが深いところまで進行している場合があります。
とくに皮膚の薄い高齢者や麻痺がある人、寝返りができない乳児などは注意が必要です。
<症状>
皮膚の損傷の度合いによってⅠからⅢ度に分けられます。
Ⅰ度:ひりひりとした痛みやうっすらとした赤みが出ます。
Ⅱ度(浅達性):強い赤みや痛み、損傷から24時間以内に水ぶくれができます。
Ⅱ度(深達性):真皮の深くまで損傷を受けると、知覚は鈍くなり痛みも少なくなります。水ぶくれも紫から白色になります。やけどの跡も残ってしまう場合が多いです。
Ⅲ度:皮膚は壊死し黒色、白色になります。知覚も機能しなくなるため、痛みを感じなくなります。跡が残ってしまいます。
<治療方法>
炎症を抑える塗り薬や傷の治りを促進する塗り薬を使います。感染予防のために抗生剤を内服する場合もあります。
やけどが進行している場合は外科的処置が必要になることがあります。
<日常生活>
・湯たんぽや電気あんかなどは布団を温める目的で使用し、就寝時に布団から取りだすようにしましょう。カバーで包んでいても低温やけどを起こすことがあります。
・使い捨てカイロは衣類の上から当てる、カイロやコタツ、電気カーペットなどを使用したまま眠らないようにしましょう。
―やけどしてしまった場合―
・まずは冷やすことが重要です。10分~30分ほど流水で冷やしましょう。皮膚がめくれたり、水ぶくれが破けてしまう場合があるため衣類は無理に脱がさずに上からで大丈夫です。水ぶくれが破けると細菌が入ってしまったり治癒が遅くなってしまう場合があります。
やけどの跡を残さないためにも低温やけどかなと思ったら早めに受診しましょう。

2021/12/27