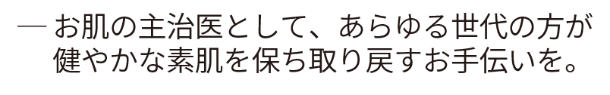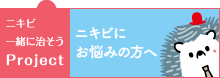お子さまの体を正しく洗えていますか?
最近少しずつ暖かくなってきましたが、まだまだ乾燥している季節が続いています。
当院ではこの時期も毎年体の乾燥により、来院される患者様が多くいらっしゃいます。
□タオルでゴシゴシこすっている
□石鹸を泡立てず、直接洗っている
□石鹸で体をしっかり洗わない
□さっと石鹸を流して終わりにしてしまう
みなさまはこのような体の洗い方をしていませんか。
入浴すると皮脂などが洗い流され、皮膚が乾燥しやすくなります。
体の洗い方を見直し、正しく保湿剤を使用するだけで、お子さまの皮膚トラブルを避けられるかもしれません。
〇タオルでゴシゴシこすっている
スポンジや目の粗いタオルなどでゴシゴシ洗うと、皮膚を傷つけてしまう恐れがあります。アトピー性皮膚炎などの疾患がある場合は出来るだけ素手で、爪を立てずに指の腹を使って洗いましょう。素手で洗うことで適度な力で洗うことができます。
〇石鹸を使わない、または石鹸を泡立てず直接洗う
お湯で洗うだけでは、皮膚の雑菌や汚れが十分に落ちません。
泡立てネットなどを使用し、石鹸を泡立てて洗うことにより、十分な洗浄効果が得られます。
〇石鹸を軽く流して終わりにしてしまう。
皮膚に石鹸の洗い残しがあると皮膚トラブルの原因にもつながります。
石鹸の洗い残しがないようにぬるめのお湯でしっかりとすすぎましょう。
お子さまの長風呂には注意が必要です。乾燥が気になる場合には、入浴後に保湿剤を使用することをおすすめいたします。
保湿剤は皮膚から水分が逃げないように“ふた”をする役割をもっており、出来れば、入浴後5分以内に、皮膚が水分を吸収しているうちに塗るのが効果的です。

低温やけどにご注意を!
使い捨てカイロ・電気こたつ・電気あんか・ホットカーペット・湯たんぽなど、寒い冬には体を温める暖房グッズがかかせませんよね。
みなさんもご自宅でお使いなのではないでしょうか?
しかし、その暖房グッズで冬に「低温やけど」をしてしまう人が増えています。
◇原因◇
私たちの体は熱湯や火など直接熱いものに触れると、その瞬間に「熱い!」と体が反応してすぐに熱いものから離れる為、皮膚の深いところまでやけどしてしまうことはそんなに多くありません。
それに対して、低温やけどは体温より少し高い40~60℃くらいのあまり熱くない熱源(湯たんぽ・カイロ・ホットカーペットなど)に長時間触れていたときに起こります。
◇症状◇
・軽い赤み
・水ぶくれ
・皮膚の痛痒さ、ヒリヒリ感
熱さや痛みを感じにくいため、気付いた時には「水ぶくれができる」などの軽度のやけどから、最悪の場合には「皮膚の深い部分の組織が壊死する」などの重症のやけどをしてしまっていることがあります。
もし、低温やけどをしてしまったら医療機関で早期に適切な処置を行う必要があります
皆さんは寝る際に暖房グッズを体の側においたまま放置してしまってはいませんか?
低温やけどは通常のやけどとは違い、見た目は軽症に見えますが、実際は皮膚の深い部分まで傷ついてしまっている場合があります。
そして気付いたときには、やけどが進行していることが多く、治療が長引いたり傷跡が残ってしまうことも…。
暖房グッズは体を温めてくれてとても便利ですが、“直接肌に触れないようにする”
“一定時間ごとに位置変え、体の同じ部分を長時間温めないようにする”ことで低温やけどにならないように注意しましょう。

2019/02/12
花粉症の初期療法について
当院では1月中旬から花粉症の患者様が増え始め、ご希望の方には保険内で受けられるアレルギー検査を実施しております。
「花粉症になってしまったかもしれない」と思っている方は、ご自身が何に対してアレルギー反応が出ているのかご存知でしょうか?
花粉にも様々な種類があり、各花粉のシーズンによりご症状があらわれる方に違いがでてきます。
ご自身がどの花粉に対してアレルギーをお持ちなのか、アレルギー検査では抗体レベルなど特定することが可能です。
原因を特定し、その花粉がいつからいつまで飛散するのかシーズンを把握することで、花粉症の症状が本格的にでる前から薬による「初期療法」を開始することができます。
この初期療法を行うことにより症状の発症を遅らせ、飛散シーズン中も症状を和らげることができ、早期に症状を改善させることができるため、結果的に処方されるお薬の量を減らすことにもつながります。
ご症状にお心あたりのある方はお早めにご来院くださいませ☆(^^)

口唇ヘルペスについて
くちびるやその周辺に軽い痒みを伴う水ぶくれができたことはございませんか?
もしかするとそれは「口唇ヘルペス」という病気かもしれません。
今回は口唇ヘルペスについて、ご説明いたします。
◇口唇ヘルペスとは?
口唇やその周りにチクチクやピリピリとした違和感や痒みが生じた後、軽度の痒みを伴う水ぶくれができる症状です。
この水ぶくれができた後は、かさぶたができて治っていきます。
身体の免疫が低下しがちな疲労時や、発熱時などに症状がでやすいといわれています。
症状の出る頻度には個人差があり、数年に1回出る方や1年に数回出る方もいます。
また、初めて症状が出る時には水ぶくれが多くできることもありますが、再発の場合、水ぶくれは少なくなり、症状が出る範囲も狭くなります。
◇原因は?
口唇ヘルペスは“単純ヘルペスウイルス”というウイルスに感染することでかかります。
このウイルスは特に水ぶくれのの中に多く存在するため、症状がでている人の水ぶくれ・唾液・涙液などに接触することで感染してしまうこともあるので注意が必要です。
◇再発するの?
口唇ヘルペスが出る頻度には個人差がありますが、再発しやすい病気です。その原因は単純ヘルペスウイルスに1度感染すると、生涯にわたって神経に潜伏するからです。
健康な時は潜伏しているウイルスは免疫によって抑えられ活動できないため症状はでません。
しかし、ストレス、疲労、発熱など免疫が低下しているとウイルスが再活性化し、症状が現れます。
◇治療方法は?
口唇ヘルペスの治療には内服か外用の“抗ヘルペスウイルス薬”を使用し、ウイルスの増殖を抑えます。この薬はウイルスが増殖しているときに効果を発揮するため、症状がでたら早めに使い始めることが重要です、
お薬により症状を軽減し、治癒を早められる効果が期待できます。
ご症状にお心当たりのある方や口唇やその周りにチクチクやピリピリとした違和感や痒みを感じる方はお早めにご受診することをおすすめいたします。

手荒れについて
だんだんと冬に近づき、この時期になると手荒れに悩む方も多いのではないでしょうか?
手荒れは「進行性指掌乾皮症」といい、水仕事など繰り返し指先に刺激が加わることで起こると考えられており、主婦・美容師・飲食店員などの方に多くみられる病気です。
今回は手荒れについてご説明いたします。
◇手荒れの症状
1、はじまり…
親指、人差し指を中心に指先がかたくなり、乾燥と指紋の消失がみられます。
2、症状が進行すると…
親指、人差し指だけでなく、全ての指に同様の症状が現れ、皮が剥けてきます。
さらに手のひらにも拡大します。
3、さらに悪化すると…
赤みやかゆみを伴い、小さな水ぶくれやひび割れもみられるようになります。
◇手荒れの原因
基本的に皮膚の水分量は一定に保たれています。通常皮膚のうるおいは3つの物質によって成り立っており、手指はその中の一つの物質である「皮脂」が少なく、十分ではありません。
皮脂とは皮脂腺から分泌される脂のことで、汗などと混ざり合って皮膚の表面を覆い、水分の蒸発を防ぐ役割をになっています。これを“皮脂膜”といいます。
皮脂が少ない手指はその代りに皮脂膜の下にある角質層が厚くなっており、皮膚を保護しています。
しかしその角質層も、石鹸や洗剤などを使用する摩擦刺激が加わると、厚い角質層は弾力を失い、ひび割れてしまいます。
◇日常生活で気をつけること
○刺激を避ける
綿手袋を着用し、指先への刺激を避けましょう。また、水仕事の際はゴム手袋を着用し、直接洗剤に触れないようにしましょう。
○手を洗いすぎない
何度も手を洗うと皮膚の水分が失われ、症状が悪化してしまいます。手を洗ったあとはハンドクリームなどの保湿剤を使用しましょう。
症状が悪化する前に受診をおすすめいたします。
皮膚にうるおいを与える塗り薬や、かゆみ・湿疹を抑える塗り薬や飲み薬があります。
症状が気になる場合には早めに医療機関を受診しましょう。

2018/11/27
風疹の自費検査について
最近、「風疹」という病気について耳にする機会が増えました。
ニュースなどでも取り上げられており、“良くわからないけど怖い病気なのかな?”とご心配されているかたも多いのではないでしょうか。
◇風疹とは
発熱・発疹・リンパ節膨張を特徴とするウィルス性発疹症です。
はしかに似ており、3~4日で治るといわれています。患者さんの咳やくしゃみで飛び散った細かい水滴の中にいるウイルスを吸い込むことで感染する飛沫感染です。
飛沫は水分を含んで重いので、ウイルスが空中を長時間漂うことはなく、空気感染の代表である麻疹(はしか)や水痘(水ぼうそう)のように感染力は強くありません。
◇風しんウィルスに感染すると?
感染してから2~3週間ほどで症状が現れ、発熱・発疹・リンパ節(とくに耳の後ろ・頸部・後頭部)の腫れがほぼ同時に出現します。
赤い細かい発疹でほぼ同じ大きさで、全身に出ますが、3~5日で消えます。
症状だけで風疹と断定することは難しく、抗体検査をしてはじめて確定となります。
子供の方が症状は軽く、大人がかかると症状が長引く傾向があります。一度感染すると免疫を獲得するのでその後風疹にはかかることはありません。
妊娠20週頃までの妊婦が風疹ウイルスに初感染すると出生時が先天性風疹症候群を発症する可能性があります。
◇風疹の予防について
男女ともがワクチンを受けて、まず風疹の流行を抑制し、女性は感染予防に必要な免疫を妊娠前につけておくことが重要です。
当院では、下記検査を自費で行っております。
・風疹抗体検査(風疹IgG) ¥4,000
ご希望の方はお電話またはスタッフまでお問い合わせください。

ケロイド治療について
◇ケロイドとは
ケロイドとは傷跡などが赤く盛り上がったり、硬く肥厚したりした状態のことをいいます。
ケロイドには2種類あり、真性ケロイドと肥厚性瘢痕(瘢痕ケロイド)に分けられます。
①真性ケロイド
小さな外傷などが元となり、そこが赤く盛り上がり、コブのようになります。特徴としては、元の外傷部位を超えて大きくなり、おさえても痛くありませんが、強くつまんだりすると痛みが生じます。
②瘢痕ケロイド
手術や怪我の痕が厚くなり、赤く盛り上がります。真性ケロイドとは異なり、隆起が元の外傷より広がらず、痒みを生じることもあります。
◇治療方法
ケロイドの治療法としては、飲み薬・塗り薬・圧迫固定具・貼り薬・注射がありますが、今回は塗布薬、内服薬についてご説明いたします。
1、塗り薬
塗り薬として効果のあるものはいくつかあります。
炎症を抑える目的でアンテベートを始めとするステロイド軟こう・クリームや、非ステロイド系抗炎症剤、ヒルドイドソフト軟膏などのヘパリン類似物質などの保湿剤を使用します。
2、貼り薬
多く利用されているのは、抗炎症剤であるステロイドがついているテープ(ドレニゾンテープ)があります。ステロイドには抗炎症効果がありますので、皮膚線維細胞の増殖を抑え、赤みやかゆみに効果が認められます。
3、内服薬
リザベン(トラニラスト)という内服薬が肥厚性瘢痕、ケロイドに対する治療薬です。
リザベンは抗アレルギー薬でもあり、ケロイドや肥厚性瘢痕にある炎症細胞が出す伝達物質を抑制することにより、傷の赤みやかゆみなどを軽減させる効果があります。
ケロイドは場所や大きさ、その他色々な条件によって、治療方法がことなってきます。
ご症状にお心当たりのある方は、まずは一度ご相談ください(^^)

MRSAについて
○MRSAとは?
MRSAとは、「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌」のことを指します。
黄色ブドウ球菌は非常にありふれた菌で、私たちの髪の毛や皮膚、鼻の粘膜、口腔内、傷口などに広く生息しており、健康な人の20~30%が保菌しているといわれています。
黄色ブドウ球菌は基本的に弱毒菌なので、抵抗力があれば無害な菌ですが、弱い人が感染すると重症になる原因となります。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の性質は黄色ブドウ球菌と一緒ですが、耐性遺伝子を持っており、抗生物質が効きにくい特徴をもっています。
○MRSAに感染すると?
皮膚の傷に伴って、化膿症、膿痂疹、毛包炎、おでき、蜂窩織炎、怪我の傷・火傷・手術後の二次感染など、皮膚組織の感染症を起こすと患部の赤み、腫れ、痛みなどがみられます。
重症化すると発熱や低体温、頻脈、低血圧などの全身症状を伴う場合もあります。
○治療法は?
各種の抗菌薬に抵抗性を示すため、治療に時間を要し、重症化することもあります。治療方法としては検査を行い、効果のある抗菌薬を調べ、その抗菌薬を用いた治療を行います。

運動誘発型アナフィラキシーについて
「運動誘発型アナフィラキシー」とは、基本的に学童期以降にみられる症状で、運動が引き金となってアナフィラキシー症状がでるアレルギーです。この症状は食べ物を食べただけでは現れず、特定の食べ物を食べてから、数時間以内に運動すると症状が現れることが特徴です。昼休みや5時間目の体育の時間、部活の時間に出やすく、中学生の男子に多くみられる傾向があります。
◇運動誘発型アナフィラキシーの症状とは?
「アナフィラキシー」とは、とても強いアレルギー反応を短時間に引き起こし、ショック症状を起こすことです。運動誘発型アナフィラキシーの症状では、運動が引き金となり、以下の症状が現れます。
・じんましん
・呼吸困難
・血圧低下
・意識消失
また、これらの症状は必ずしも運動の激しさと関係している訳ではなく、軽い運動でも引き起されることがあります。
◇どうして起きるの?
特定の食べ物を食べた後の運動がきっかけとなり、肥満細胞というアレルギー反応で重要な役割を担う細胞からヒスタミンという物質が放出されます。このヒスタミンが気管支を収縮させて呼吸困難を引き起こしたり、血管透過性を高めて血管の外側の組織に体液を漏出させることで浮腫みや血圧低下を引き起こします。
◇どうすればいいの?
・運動中に症状がでたら、運動をやめて安静を保つ。
・食事のあと2時間は安静にして運動しないこと。
・症状が進んでいく場合、医療機関を受診し、処方された薬を内服する。
※呼吸苦などの重度の症状が出ていたら、すぐに救急を受診する。
発症経験がないにも関わらず、そういう症状が起きたら怖いからと「運動は控えた方が良い」と考える必要はありませんが、アレルギー症状がある方や、「もしかして…」と症状に心当たりのある方がいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。

2018/06/25
血液型検査できます。
☆血液型とは?
現代において、血液型がなんの役割を果たしているのかはまだよく分かっていませんが、様々な分野でとても重要な役割を担っています。
現在、赤血球の血液型は、約300種類が発見されています。
今回は、ABO血液型、Rh血液型についてご説明いたします。
<ABO血液型>
血液型は抗原(A、B)から作られています。赤血球の表面にある血液型の物質を“抗原”といい、血清の中にある赤血球と反応する物質を“抗体”といいます。ABO血液型では、赤血球(抗原)の検査と血清(抗体)の検査を行って、これらの抗原の組み合わせで、A/B/O/AB型の4種類に分類します。
→A型…赤血球+A
→B型…赤血球+B
→AB型…赤血球+AB
→O型…赤血球+何もついていない
また血清中のには、自分の持っていない抗原と反応する抗体が存在します。
<Rh血液型>
Rh血液型はABO血液型の次に重要です。この血液型にはC、c、D、E、eという主に5つの抗原があります。特にこの中のDが重要になり、赤血球にDを持っている人をRh(+)、持っていない人をRh(―)と呼んでいます。Rh(―)の人は、日本人の中で0.5%の割合となっており、200人に1人ととても少ないです。
当院でも、自費で血液型検査(¥3,000)が可能です。
1週間程で検査結果が分かりますので、ご興味のある方はお気軽にスタッフまでお声掛けください。

2018/06/15